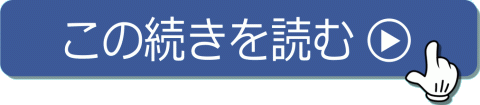2013年8月24日
電動アシスト自転車業界に忍び寄る「韓国メーカー」の影
日本の電動アシスト自転車とは、日本が開発し、そして成長させたガラパゴス的な商品であった。
その誕生は、厳しい道路交通法の中で、自転車としての規格内で原動機を搭載するという、かなり奇跡的なものであったと言ってもよい。
「アシスト」という言葉が重要であり、その機構だけ見れば、「原動機付き自転車」というジャンルがピッタリそうではあるが、これでは自動二輪、いわゆるバイクになってしまい、免許やヘルメット、税金の有無のほか、厳しい法律の制約を受けることとなってしまう。
この限りなく原動機付き自転車を、バイクではなく、自転車としての枠内に収め、そして商品化したヤマハには感謝しなくてはならないのかもしれない。
そしてこのグレーな領域に踏み込み、電動アシスト自転車というジャンルを確立できたのも、お上と繋がりの深いヤマハだったからこそ、実現できたのであり、ブリヂストンやパナソニックでは法律の壁を突破できなかったのではないかとの噂さえ聞いたことがある。
https://fiction-cycles.blogspot.com/2013/08/blog-post.html電動アシスト自転車業界に忍び寄る「韓国メーカー」の影
2013年7月29日
Panasonic「ジェッター」のディスクブレーキ化
現在発売されているモデルの中級以上には「カンチ台座」すら存在しないのが当たり前となってきている上に、ロードバイクでもディスク化への動きは出てきている。
自転車は少ないパーツ構成で多機能化するために、各パーツが様々な役割を担ってきた歴史があるが、21世紀に入り、それぞれのパーツが自分の本分に専念する傾向が強くなってきたと言える。
自動車業界では「単能工」と「多能工」という言葉があるが、自転車で例えるならば、ロードバイクは多能工、MTBは単能工である節が強い。
例えば、ロードバイクのフレームは衝撃の吸収性が重要視されているが、MTBのフレームは強固に全体を支えることが重視されている。
なぜなら、MTBの衝撃吸収はサスペンションという別の部門が専門で担当しているからだ。
今回のテーマのディスクブレーキにおいても同じことが言えるだろう。
「ディスクローター」という円盤状のパーツがあるが、これは本来であれば、ホイール(リム)が受け持っていた機能である。
これがなぜ分業制になったかと言えば、機材の進歩の中で、ホイールはより軽く、より強く、より空気抵抗を少なくと求められたため、ブレーキの構成部品の一員でいられる余裕がなくなったのである。
同時にブレーキはより制動力を高く、より確実に、よりコントロールしやすくというニーズの中でディスクブレーキという独立した構造に進化して行ったと言ってよい。
それに対してロードバイクにおいては、軽量化というテーマが何十年に渡り課題とされていたため、部品点数を増やすという行為に対して否定的であった。
しかし、技術のレベルが向上し、UCIの定める最低重量の6.8kgが簡単にクリアできるようになってしまった現在においては、これ以上の軽量化は無意味であり、次に向かう先として予想されるのはやはりMTBが先に辿ったように、それぞれの機能への追求ではないだろうか。
ロードバイクのディスクブレーキ化も、そう考えれば納得が行く。
https://fiction-cycles.blogspot.com/2013/07/panasonic.htmlPanasonic「ジェッター」のディスクブレーキ化
2012年11月10日
自転車フレームの接合方法
一般的に自転車のフレームといえば、金属の丸いパイプが組み合わさってできている。
「そんなことは小学生でも言っている」と言われそうだが、ではパイプ同士がどうやって繋がっているのかということを詳しく答えられる人は多くないだろう。
まず材料と材料を繋ぎ合わせる方法は、大きく分けて3つだ。
・溶接する
・接着する
・ネジやリベットを利用して固定状態を維持する
自転車の場合、上2つが一般的であり、ボルトオンという手法は限られる。
自転車は人力で動かすものという点から、重量的に不利となるネジ止めはフレームにはほとんど使用されないが、反対に整備が必要となる付属品はすべてと言っていいほどネジで固定されている点は、自転車の不思議とも言えるが・・・。
「そんなことは小学生でも言っている」と言われそうだが、ではパイプ同士がどうやって繋がっているのかということを詳しく答えられる人は多くないだろう。
まず材料と材料を繋ぎ合わせる方法は、大きく分けて3つだ。
・溶接する
・接着する
・ネジやリベットを利用して固定状態を維持する
自転車の場合、上2つが一般的であり、ボルトオンという手法は限られる。
自転車は人力で動かすものという点から、重量的に不利となるネジ止めはフレームにはほとんど使用されないが、反対に整備が必要となる付属品はすべてと言っていいほどネジで固定されている点は、自転車の不思議とも言えるが・・・。
https://fiction-cycles.blogspot.com/2012/11/blog-post.html自転車フレームの接合方法
6.54kgのクロモリバイク ミヤタ「Elevation Extreme」
一昔前のロードレーサーの完成車重量といえば、8~9kgの間であればレース機材として標準的とされる時代だった。
それがマテリアルの進化とともに、急速に超軽量バイクが市場に現れ、今や実用面の問題を含めても誰しもが6kg台のバイクを手に出来る時代となった。
それこそ15年ほど前までは、一部のブルジョア層以外は何の抵抗も無くクロモリバイクに乗っていたし、周りも人々ほぼ同じスペックだったので、特に問題は無かった。
それからしばらくし軽量化は加速。
アルミニウムという素材が台頭し、最近ではカーボンバイクでなければレース機材にあらずといったところまで世間に浸透している。
そのため、100年以上の歴史を有するクロモリをはじめとするスチールバイクはすっかり過去の遺物にまで成り下がってしまった。
やはりスチールではダメなのか・・・
たしかに一部マニアの間や、ロングツーリングなど、クロモリの良い部分にこだわるユーザーは確かにいた。
しかし重量という壁の前ではどうすることもできない場合がある。
そう、レースの世界である。
今回ミヤタが発表した「Elevation Extreme」という6.54kgのロードレーサーは重量も驚くべき点ではあるが、もっと意外だったのはミヤタのHPを見れば分かるが、しきりに「戦うためのバイク」「ヒルクライム」という言葉が登場する。
https://fiction-cycles.blogspot.com/2012/11/654kgelevation-extreme.html6.54kgのクロモリバイク ミヤタ「Elevation Extreme」
2012年10月8日
あさひオリジナル電動「enersys(エナシス)」
世の中には二通りの人間がいる。
新商品が出たらすぐに欲しくなってしまうタイプと、世間の評価をじっくり吟味してから購入を検討する慎重派タイプだ。
失敗をしたくないのであれば後者だが、「目新しさ」という価値を手に入れるには前者しかないだろう。
当然ながらフィクションサイクルは新しいものに目がないので、すぐに飛びついてしまうのであるが、電動アシスト自転車といえば高価な買い物。
おいそれと何台も購入する訳にはいかない。
そんなときはやっぱり持っている人に借りるのが一番手っ取り早い訳で・・・。
「ちょっとだけ貸して頂戴」などと言いながら飽きるほど乗り回してみた感想を書く。
https://fiction-cycles.blogspot.com/2012/10/enersys-airpur.htmlあさひオリジナル電動「enersys(エナシス)」
登録:
投稿 (Atom)
人気のトピックス(全期間)
-
メリダ(MERIDA)といえば台湾を代表する世界的な自転車メーカーであり、その規模は業界最大手のGIANTに続く二番手を行くトップメーカーだ。 しかし日本での知名度は低く、トレックやキャノンデール、スペシャライズドといった花形ブランドの影でひっそりとしている印象がある...
-
今や完組みホイール全盛期で手組みホイールのシェアは「風前の灯」と言っていい。 フィクションサイクルが手組みホイールの終焉を予感したのは遡ること10年以上、あの名作ホイール「MAVIC KSYRIUM」を手にした瞬間だった。 完組みならではの自由な設計と、理想的なスポーク...
-
世の中に50mmハイトのカーボンホイールはどのくらいの種類があるだろうか。 DURAのC50、MAVICのコスミック、フルクラムのレーシングスピード、そしてカンパのボーラ・・・ 数えだしたらキリが無いほどのホイールが存在する、まさにディープリムの王道、50mmハイトカテゴ...
-
デュラエース (DURA-ACE) は、シマノが作るロードバイク用のコンポーネントである。 同社ではコンポーネントにグレードを設けて販売しているが、その中で最高峰に位置する。 シマノは現在多くの部品を海外工場で生産しているが、マウンテンバイク向けの最高級コンポーネントである...
-
自転車界の本当の巨人といえば、台湾のGIANTではなく、日本の「シマノ」だろう。 こんなことを今更言うのもなんだが、自転車を扱うということは、全てがシマノの利益に繋がっていると言っても過言ではない。 よく安価な通販商品にて「日本ブランドのシマノのパーツを使用しています...
-
リチウムイオン二次電池の安全で正しい使い方 01.電池を高温になる場所に放置しない 02.電池を熱源のそばに放置しない 03.取り扱い説明書を読む 04.電池を濡らさない 05.電池は決められた充電器、ACアダプターで充電する 06.電池は充電器や機器に正しく...
-
始めに言うと、 ブリジストンタイヤはサイクル用タイヤを作ったことが過去に一度も無い 、というのが業界内での常識だ。 ※ブリヂストンタイヤ=株式会社ブリヂストン 以前まで、いわゆるママチャリ用などの一般タイヤはIRC(井上ゴム工業)のOEM生産が多く、インドネシ...
-
こんなタイトルを自転車屋が書くとは、身内や同業者から批判が出そうな気もするが、スペックを読む限り有名ブランドのカーボンホイールとどこが違うのか、はやり販売店としては確認しておかなければならない。 という言い訳を用意しつつ、レビューをおこなってみたいと思う。 世の中では...
-
フィクションサイクルの代名詞とも言われるエアインプレ 今回のターゲットはテレビでも放送され話題になっているフリーパワーと呼ばれる特殊な自転車用クランクだ。
-
TEAM LAMPRE-MERIDA が採用するCF4 lite MC フレームを搭載したレプリカモデル チームからの要望により作られたオールラウンドなパフォーマンスを実現するSCULTURA CF4 lite MCフレームを採用。Shimano Dura-Ace や...